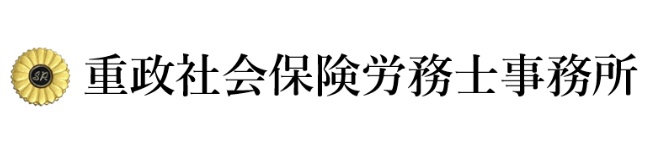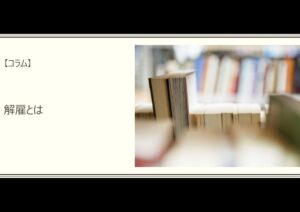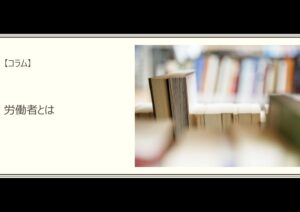【コラム】勤怠管理に関して
勤怠はどの様に管理する?
会社ごとに出社、退社、休憩等の管理方法が違いますが、法律ではどの様に定められているのでしょうか?
労働安全衛生法
第66条の8の3 事業者は第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
労働安全衛生規則
第52条の7の3第1項 法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
肝心なのはその時刻の客観性、信憑性です。その為、本人と1名以上の確認があった上で記録を行っていく等の状態が理想ですが、現実ではなかなかそこまでは出来ません。その為、現場にいないと記録が出来ない、管理者以外修正が出来ない等、最低限正確な記録を残す工夫が求められます。前項の最後に「その他適切な方法」とありますが、例として自己申告等が挙げられます。ただし、客観的かつ信憑性がある記録を残す必要がある本作業において、自己申告をそのまま記録とするのではなく、管理者のチェックを入れる等、正確な記録を行う工夫が求められます。
勤怠管理の重要性
勤怠を正確に行わないといけない理由は様々ですが、まずは働いた時間に応じた給与を正しく支払う為という理由が挙げられます。働いた時間分の給与が支払われない、逆に働いていないにもかかわらず給与が発生しているというのはどちらも違法性が問われます。その為、労使共にしっかりと勤怠を管理し、契約に応じた正確な給与を支払っていく必要があります。もう一点は従業員の健康管理の観点です。特に法定時間外の労働の管理は従業員の体調不良に直結していくため、時間の管理は当然ながらその時間に応じて健康面にも気を付けていく必要があります。
勤怠管理にはITツールの利用が便利です。
現在では勤怠に関し、様々なITツールが登場しています。スマホ等で勤怠が入力できれば、建設業などの外部で仕事をする業種であっても勤怠管理がしやすく、給与計算等も自動化が可能です。また、勤怠に関しては法定帳簿として法律で保管が義務付けられており、ITツールを使った管理ではその保管も非常に簡単にできます。勤怠管理に困られている企業様は是非ご検討ください。